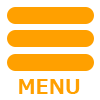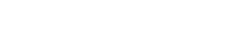ご挨拶

当院は2008年3月、千葉市稲毛区に開院いたしました。病院の名称には当院のモットーである「こころのこもった医療を提供したい」という想いが込められています。また、地域の皆様に覚えてもらいやすく、あたたかみのある平仮名での表記としました。「家族の一員」である動物たちに「丁寧で的確な診療」を心がけています。飼い主様と動物たちにとってより良い暮らしをサポートしていきたいと思っておりますので、何でもお気軽にご相談ください。
当院で対応できない高度医療に関しては二次診療施設(大学病院、専門検査機関、各科専門病院、日本小動物医療センター、キャミックなど)を迅速にご紹介・アドバイスを行っています。
スタッフ紹介
獣医師
経歴
- 日本獣医畜産大学 2003年卒業
(現 日本獣医生命科学大学卒業) - 千葉県市原市の市原・山口動物病院勤務
- 埼玉県川越市の霞が関動物外科クリニック勤務
所属学会など
- 千葉県獣医師会
- 千葉市獣医師会
獣医師
経歴
- 日本獣医畜産大学 2003年卒業
(現 日本獣医生命科学大学卒業) - 千葉県市原市の市原・山口動物病院勤務
- 埼玉県所沢市の日本小動物医療センター勤務
スタッフ


診療案内
○内科疾患
下痢や嘔吐、風邪など日常よくある疾患から、代謝疾患や消化器疾患などの複雑な病気まで、動物にもさまざまな内科疾患があります。当院では問診・触診の後、必要に応じて各種検査を行います。診断の上、より高度な治療を要する場合は専門医と連携をして治療を進めます。
○外科疾患
外傷、腫瘍外科、皮膚形成、腹腔内外科など外科全般を得意としております。外科手術が必要な場合でも安心してお任せください。
○予防医療
狂犬病、混合ワクチン、フィラリア、ノミダニ予防などの各種予防接種を行っております。ワクチンによって防げる病気はたくさんあります。大切な家族の一員である動物たちを病気などから守るためにも、定期的な接種で予防を心がけましょう。
○避妊・去勢手術
避妊・去勢手術は、望まれない子犬や子猫を増やさないという目的はもちろんのこと、乳腺腫瘍、卵巣腫瘍、子宮蓄膿症、会陰ヘルニア、前立腺肥大などホルモンによる病気の予防、またストレスの防止になるといわれています。ご不明な点、心配なことがございましたら獣医師にご相談ください。
○定期健診
言葉を話せない動物たちは病気の発見が遅くなりがちです。定期的に健康診断を受けておくことで、異変が起きても普段との違いに気づきやすくなります。当院では病気の早期発見・治療のためにも、年1回の定期的な健康診断をお勧めしています。
○整形外科
膝蓋骨脱臼、股関節形成不全、靭帯断裂、椎間板ヘルニアなどの手術は難易度も高く、治療ができる病院は限られていますが、当院にぜひお任せください。手術内容やその後のリハビリなどのご説明をし、納得いただいた上で治療いたします。
○トリミング
トリミングはシャンプーやカットだけではなく、健康管理の一環と考えています。皮膚病をはじめ動物たちの体調をしっかりと観察し、トリマーと連携をしながら丁寧に施術を行います。
○皮膚疾患
「アレルギーは治らない」と治療をあきらめていませんか?確かに治すことは難しいかもしれません。しかし、当院ではより詳しい検査や多様な治療法をご提示することにより、動物たちのより良い生活の質を確保できると考えております。また、アレルギーだと思っていた病気が全く違う病気であることもあります。適切な治療により治せる皮膚病は治してあげましょう。イボなどの治療には凍結療法を用いた治療も行っております。
○内分泌疾患
内分泌疾患は実は犬には比較的多い病気であるにも関わらず、無治療のままでいることが多い病気です。皮膚症状も出る場合が多いのですが、単純に皮膚病あるいはアレルギーと診断され、なかなか治らないことも多いようです。当院では疑わしい場合には積極的に検査をし、治療をお勧めしています。